「スヴァールバル諸島では、生まれてはいけない──」
そんな噂を耳にしたことはありませんか?
一見すると都市伝説のようですが、実はまったく根拠がないわけでもないんです。
私はいま、北極圏にあるスヴァールバル諸島で暮らしていて、昨年はこの“赤ちゃんが生まれない島”で妊婦生活を送りました。
「本当に出産は禁止されているの?」
「もし妊娠したらどうなるの?」
そんな素朴な疑問に、自分自身が直面したのです。
この記事では、噂の真相を私の体験談とともにご紹介します。
少し変わった極地の出産事情を、どうぞ覗いてみてください。
スヴァールバル諸島で赤ちゃんが生まれない本当の理由

「スヴァールバル諸島では生まれてはいけない」と言われる理由は何でしょうか?
実際のところ、出産を禁止する法律は存在しません。
ただし、島には妊婦さんを受け入れるだけの医療体制が整っていないのです。
中心地のロングイェールビーンには小さな病院がひとつありますが、産婦人科も分娩室もなく、助産師さんが一人勤務しているだけ。
もちろん、24時間いつでも安心してお産できる環境ではありません。
それでも、もし早産や緊急事態が起これば、この病院で赤ちゃんが取り上げられることもあります。
実際、2000年代以降にロングイェールビーンで生まれた赤ちゃんはわずか3人。
最後のケースは2009年、双子の赤ちゃんが帝王切開で誕生しました。
つまり「生まれてはいけない」のではなく、「ここで赤ちゃんが生まれるのは極めてまれ」というのが本当のところなんです。
出産場所の選び方|本土?実家近く?それとも母国?
スヴァールバル諸島で妊娠した場合、どこで出産するかは一応、自分で決めることができます。
ただし、実際のところ現地のロングイェールビーン病院は分娩に対応していないため、選択肢にはほとんど入りません。
一番近い出産可能な病院は、飛行機で約1時間半の場所にあるトロムソの北ノルウェー大学病院(UNN)。
ここで出産する人も少なくありませんが、ノルウェー人の多くは「どうせ移動するなら」と実家の近くにある病院を希望することが多いようです。
また、この島には外国籍の住民も数多く暮らしていて、私のような外国人妊婦もめずらしくありません。
そうした人のなかには、一時的に母国へ戻って出産するケースもよくあります。
ノルウェー本土では「里帰り出産」は一般的ではありませんが、医療体制が限られたスヴァールバルで妊娠してみると、やはり家族のそばで安心して出産したい──そんな気持ちになるのも自然なことだと思います。
極地の妊婦生活|驚きと発見の日々

妊婦健診はまさかの2泊3日!飛行機で行く小旅行
ノルウェーの妊婦健診は、日本に比べるととてもシンプルです。
健診の回数は最大で10回、超音波検査は基本的に1回だけ(希望すれば2回まで)。
高齢出産やリスクがある場合には追加されることもありますが、それでも回数は少なめ。
日本のように毎回エコー写真で赤ちゃんの成長を見られるわけではありません。
私も妊娠初期のころは「えっ、たった1回?」とびっくりしました。
日本では健診のたびに超音波検査を受けるのが当たり前で、赤ちゃんの姿を見るのを楽しみにしている人も多いですよね。
私自身、少し物足りなさを感じたのも正直なところです。
それでも振り返ってみると、「1回だけでよかったのかもしれない」と思えるようになりました。
その理由はスヴァールバルの医療事情にあります。
島内には超音波検査の設備がなく、検査を受けるには本土のトロムソにある大学病院まで行かなくてはなりません。
飛行機で片道約1時間半。フライトの関係で、健診を受けるだけでも最低2泊3日の滞在が必要です。
仕事や生活の調整、そして妊婦の体への負担を考えると、頻繁に通うのはやはり大変。
赤ちゃんの様子をあまり見られないのは少し寂しいですが、移動のストレスが少なくて済んだのは結果的に助かったなと感じています。
助産師さんが半年ごとに交代!?へき地ならではの医療事情

へき地医療の課題としてよく挙げられるのが、医療従事者の不足。
北極圏にあるスヴァールバル諸島でも、それは例外ではありません。
この島では小児科と妊娠・出産のケアを、たった一人の助産師が担っています。
しかもその助産師さんは半年ごとの交代制。つまり妊娠中に何度も担当が変わるのです。
私の場合、妊娠から産後1年までの間に3人の助産師さんにお世話になりました。
最初の健診では、こんなことを言われて思わずびっくり。
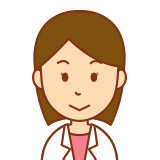
昨日スヴァールバルに着いたばかりで、今日が初勤務なの!
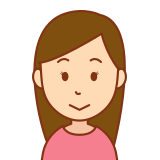
えっ!?本当に大丈夫!?
最初は正直不安になりましたが、実際に担当してくれたのは60代前後のベテラン揃い。
どの方もとても親切で頼もしく、安心してお任せすることができました。
ただ、もうひとつ驚いたのが「助産師さんがいない時期」があること。
ノルウェーは休暇文化が徹底しているため、派遣期間と次の交代の間に空白ができてしまうのです。
私が妊娠していたときも、
- 12月(クリスマス休暇) → 助産師不在
- 7月・8月(夏の長期休暇) → 助産師不在
という状況でした。
結局、私が受けた健診は全部で7回。
日本では14回程度が一般的なので、ほぼ半分の回数です。
初回の健診から2回目まで約3か月空いたり、妊娠後期にも2か月まったく健診がなかったりしました。
幸い経過は順調だったので問題はありませんでしたが、もしトラブルがあったら…と考えるとやっぱり怖い。
助産師が常駐していないことや健診の少なさに、不安を感じる妊婦さんは少なくないと思います。
出産のためにノルウェー本土へ移動!

意外とゆるい?本土移動の“出産ルール”
スヴァールバル諸島では、妊婦は出産予定日の約3週間前までに島を離れ、本土へ移動することが求められます。いわゆる「出産ルール」です。
もともとは「予定日の1か月前までに移動」とされていましたが、現在は少し緩和されて3週間前が目安になっています。
ただし、このルールは厳格に管理されているわけではありません。
実際は自己申告制で、妊娠32週ごろに受けるスヴァールバルでの最後の健診のときに、助産師さんへ出発日を伝えるだけ。
診断書も用意してもらえますが、私の場合は一度も提示を求められませんでした。
そのため、実際には予定通りに出発しないケースも珍しくありません。
私の周りでも「結局2週間前に本土へ移動した」という話を聞いたことがあります。
滞在先選びで予想外のトラブル回避!病院ホテルの落とし穴

私は出産に向けて、スヴァールバル諸島から最も近く移動の負担も少ないトロムソを出産先に選びました。
そこでまず悩んだのが「どこに泊まるか」ということ。
トロムソには家族など頼れる人がいないため、出産前後の約4週間を過ごす滞在先を自分たちで確保しなければなりませんでした。
選択肢は主に次の3つ。
- 病院に併設されたホテルに泊まる
(妊婦は無料で利用でき、朝夕の食事もついてきます) - 市内のホテルやアパートを自分で予約する
- その両方を組み合わせる
病院のホテルは安心ですが、家族も一緒に泊まる場合は1泊550NOK(約7,700円)+食事代がかかります。
さらに部屋はキッチンなしのワンルーム。1か月間ほぼ外食生活になるのは現実的ではありませんでした。
そこで前半はアパート、後半は病院のホテルに泊まる計画を立てていたのですが……最終的に、病院から徒歩10分ほどのAirbnbのアパートを予約することに。
この決断が、思わぬトラブルを避けることにつながりました。
ちょうどその時期、病院のホテルでノロウイルスが流行し、妊婦と新生児の宿泊が禁止に。
さらに観光シーズンが重なり、市内のホテルはどこも満室。直前に数週間分の滞在先を探すのは、ほぼ不可能な状況でした。
もし病院のホテルを選んでいたら…と思うと、今でもゾッとします。
最後にアパートを選んだのは偶然でしたが、本当にあのとき決断してよかったとしみじみ感じました。
産後はどう帰る?スヴァールバル帰宅のリアル

赤ちゃんにパスポートは必要?意外な解決法
妊娠中、ずっと気になっていたことがありました。それは──
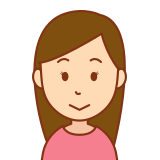
新生児にもパスポートは必要なの?
スヴァールバル諸島はノルウェー領でありながらシェンゲン協定には加盟していません。
そのため、ノルウェー本土との行き来には必ずパスポートチェックと入国審査があります。
ということは、通常のルールに従えば「赤ちゃんのパスポートをトロムソで申請・取得するまで、スヴァールバルの自宅に戻れないのでは?」と考えてしまったのです。
とはいえ、パスポートの取得はそう簡単ではありません。
申請は警察署の窓口で行う必要があり、予約も取りづらい。
しかも生まれたての赤ちゃんは、その場で証明写真を撮らなければなりません。
「首も座っていない新生児の証明写真ってどうやって撮るの?!」
と、想像するだけでハードルの高さに頭を抱えていました。
そんな心配をよそに、結果的には赤ちゃんのパスポートがなくてもスヴァールバルへ戻ることができました。
トロムソの病院で発行された出生証明書が、臨時のパスポート代わりになったのです。
助産師さんによると、トロムソ以外で出産した方の中には、パスポートがなくてトラブルになったケースもあったそう。
それを聞いて余計にドキドキしましたが、トロムソの空港スタッフは慣れた様子で出生証明書を受け取り、問題なく通過できました。
こうして無事に赤ちゃんと一緒にスヴァールバルの自宅へ戻ることができ、本当にホッとしました。
生後8日目で飛行機デビュー!極寒の子育てスタート

わが子と一緒にスヴァールバル諸島へ戻ったのは、生後8日目のことでした。
この島には大きな病院や専門的な設備がないため、出産後は最低でも6日間、病院で赤ちゃんの経過を観察するようにと指示されていました。
ノルウェーの産後ケアはシンプルで、母子ともに問題がなければ出産から2日ほどで退院するのが一般的ですが、私は少し長めに入院し、生後5日目で退院しました。
退院後は臨月に借りていたアパートに戻ったものの、やはり“仮の住まい”。
ベビー用品も最低限しか持ってきていなかったので、お世話の面でも不便さを感じていました。
そこで予定より早めにスヴァールバルの自宅へ戻ることを決め、航空券を探すことに。
ところが観光ハイシーズンだったため直前のチケットはほとんど満席。なんとか確保できたのが、生後8日目の便でした。
こうして産後まもない体で、大量の荷物と小さな赤ちゃんを連れての移動に挑むことに。
しかも到着した日のスヴァールバルは気温マイナス17度。
退院後初めての外出が、いきなり極寒の世界というインパクト抜群の体験となりました。
日本では「1か月健診までは自宅でゆっくり」という考えが一般的ですよね。
けれどノルウェーや北欧では「赤ちゃんは積極的に外に出すもの」という文化が主流。
新鮮な空気を浴びることが健康によいとされ、生まれてすぐのお出かけもめずらしくありません。
スヴァールバルでも、生後まもなくベビーカーでお散歩デビューするのが当たり前。
私の子どもが生まれたのはマイナス20度ほどの寒さが続く時期でしたが、ちょうど極夜が明けて太陽の光が戻ってきた頃で、助産師さんからも「お散歩に行きましょうね」と勧められたほどです。
こうして、わが家のスヴァールバル育児生活がスタートしました。
厳しい自然のなかで、母子ともに少しずつたくましくなっていくのを感じています。
出産費用は無料!でも意外と出費が…
ノルウェーでは、スヴァールバル諸島に住んでいる妊婦さんも妊婦健診や出産の費用は基本的にすべて無料です。
本土の病院で出産する場合、航空券や食費、宿泊費に対して一定の補助が出ます。
外国人でも条件を満たせば、ノルウェー人と同じ医療サービスを受けられます。
私自身も出産そのものに費用はかかりませんでしたが、実際には自己負担になる部分もありました。
たとえば検査費用や、本土での滞在費などです。
なかでも出費が大きかったのはトロムソでの宿泊費。
本土で出産する妊婦は、少なくとも4週間は滞在できる場所を自分で確保しなければなりません。
補助金はありますが、支給されるのは「実際に宿泊した日数分」だけ。
私の場合は出産が予定より早まり、入院も少し長引いたため、補助対象になったのは15日分だけでした。
1泊あたりNOK 680(約9,500円)が支給されましたが、それでも最終的には宿泊費だけでNOK 16,000(約22万円)の赤字に…。
なお、妊婦本人だけであれば病院併設のホテルを無料で利用できます。
ただし部屋が狭くキッチンもないため、約1か月の長期滞在となると実際に使っている人はあまり多くない印象です。
私の周りでも「実家に滞在した」あるいは「ホテルやアパートを自分で予約した」という人がほとんどでした。
ちなみに、食費に関しては1日あたりNOK 262(約3,700円)が支給され、飛行機での移動費は全額補助。
出費はゼロではありませんでしたが、それ以上に手厚いサポートに助けられました。
まとめ|“生まれてはいけない島”の真相と実際の出産事情
「スヴァールバル諸島では生まれてはいけない」──そんな言葉だけを聞くと驚いてしまいますが、実際には出産を禁止する法律があるわけではありません。
医療体制の都合から、本土での出産が推奨されているだけのこと。
妊婦さんが「安心して出産できる場所」を選んだ結果、この島では赤ちゃんがめったに生まれないのです。
私自身もこの環境のなかで妊娠・出産を経験し、「不便さ」よりも「工夫や人の温かさ」に支えられている暮らしを実感しました。
妊娠や出産に限らず、スヴァールバルには“ちょっとユニークなルールや習慣”がまだまだたくさんあります。
これからも、そんな北極圏ならではの生活の一端を少しずつお伝えできたらと思います。


